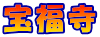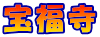宝福寺は岡山県総社市井尻野にある臨済宗東福寺派の寺院である。
地方の中でも有力な禅宗寺院である。
宝福寺は創建の年代は不明であるが天台宗の僧・日輪によって開かれたとされ、
元来は天台宗の寺院であった。
鎌倉時代の貞永元年(1232年)に備中国真壁(現在の総社市真壁)出身の
禅僧・鈍庵慧總によって禅寺に改められた。
宝福寺は最盛期には塔頭55、末寺約300寺の大寺院となり隆盛をきわめましたが、
戦国時代に備中戦乱が起こり三重塔を残してことごとく灰燼に帰しました。
写真は明治時代に復元された山門です。
江戸時代には仏殿・方丈・庫裡などの七堂伽藍が復興され
近世禅宗寺院として現在に至っています。
室町時代の画僧雪舟が修行したことで有名な寺院である。
幼少より絵が上手であった雪舟のエピソードとして鼠の絵の話が残されている。
絵を描くことが好きであった雪舟少年は修行もそこそこに絵ばかり描いていた。
修行に身を入れさせようと禅師は雪舟を柱に縛り付けて反省を促した。
夕刻、様子を見に来た禅師は逃げようとする一匹の鼠を見つけ
捕まえようとしたが動かなかった。
よく見るとそれは雪舟が流した涙を足の親指で描いたものであったという。
それ以来、禅師は雪舟の絵を咎めなくなったといわれている。 。
宝福寺では毎年8月の初めから暁天座禅午前4時半から行っている。
40数年前に仲間と一緒に数年間暁天座禅に参加した。
高梁川にテントを張って翌日早朝に座禅を組み、その後出勤した
懐かしい思い出がある。
|